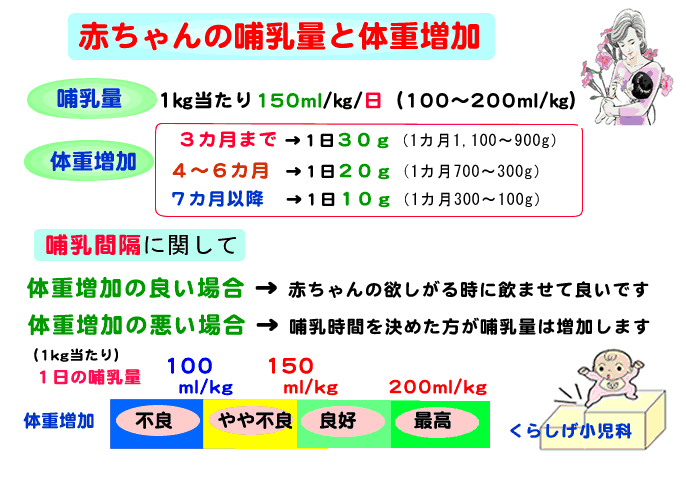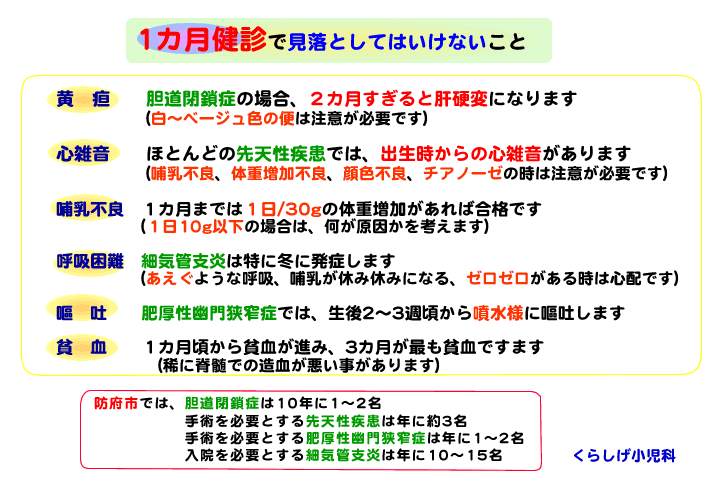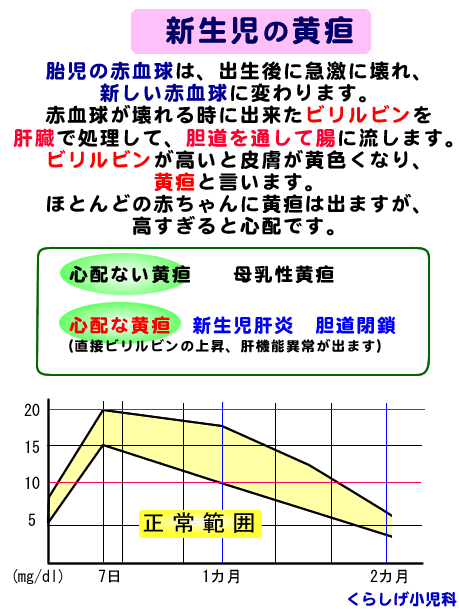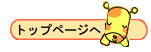産婦人科を退院してから1カ月健診までの間に、いろいろと気になる事があると思います。
お母さん方から多く聞かれる心配点や、小児科医として特に、
「1カ月健診の時に、注意して観察する大切なポイント」を
ならべてみました。
1.体重増加に関して
赤ちゃんは生まれてから1ヶ月で約1,000g体重が増えます。
産科を退院後1日平均で約30g増えていれば心配いりません。
体重増加が1日平均15g以下の場合は体重増加不良です。
原因が何かを一緒に見つけましょう。
●体重増加の悪い時
体重増加が1日15g以下の場合は、何か原因があるかを
考えます。
「母乳の出がまだ少ない場合」や「ちょこちょこ飲む」
ため哺乳回数は多くても哺乳量は増えていない場合も
あります。哺乳のリズムをつけるために、3時間間隔
で哺乳することを勧めます。
1回の哺乳量の目安は体重1kg当たり20mlです
(例:4kgなら一回哺乳量80ml)。
2.黄疸に関して
ほとんどの新生児で生後2日目頃から認められ、7日目頃
には薄くなりますが、1カ月時に黄疸が残っていることも よくあることです。
そのほとんどは、主に母乳が関係する「生理的黄疸」で
心配ありません。
しかし、稀に胆道の閉鎖を原因とする「胆道閉鎖症」や
「新生児肝炎」による黄疸があります。
「胆道閉鎖症」は1万人に一人の割合で発症しますが、
2カ月までに診断をつけ、治療を開始しなければ肝硬変
に進行します。
便の色が黄色でなく、白〜ベージュ色の時には注意が必要
です。
3.心雑音に関して
ほとんどの先天性心疾患では出生早期から心雑音が
あります。
心雑音のある児でも手術が必要になる児はわずかです。
哺乳不良、体重増加不良、チアノーゼのある時は注意が
必要です。重症の先天性心疾患は、出生後早期にチアノ
ーゼや多呼吸、哺乳不良をきっかけに見つかります。
しかし、稀に1ヶ月健診で重症の先天性心疾患の児が
見つかることもあるので心雑音のある場合は心エコーを
行います。
4.呼吸困難
赤ちゃんは気道が細く、首が顎で圧迫されがちのために
ゼロゼロという呼吸音が聞かれやすいです。
特に、冬場はRSウイルスによる細気管支炎を起こしがち
で、呼吸困難が顕著になることがあります。
あえぐような呼吸や、哺乳が休み休みになる、ゼロゼロが
ある時は心配です。早めに受診してください。
夜眠れていて、哺乳も普通に出来ていれば安心です。
5.嘔吐
赤ちゃんはよく吐きます。体重増加が良ければ心配ありま
せん。
心配な嘔吐としては、生後2〜3週頃から噴水の様に嘔吐
する「肥厚性幽門狭窄症」があります。
6.貧血
赤ちゃんは生後1ヶ月頃から次第に貧血になり、生後2〜 3ヶ月頃に最も貧血が強くなり生理的貧血とよばれます。
生まれて1ヶ月間は赤血球があまり作られず、生後3ヶ月
までは急激に体重が増える事が大きな原因で心配ありませ
ん。
貧血がひどいと蒼白・哺乳力低下・多呼吸・頻脈・無呼吸
になります。
非常に稀に骨髄での造血が悪いことがありますので、貧血
が強い場合は血液検査をします。
防府市での発症:胆道閉鎖症は10年に1〜2名
手術を必要とする先天性心疾患は年に3名
手術を必要とする肥厚性幽門狭窄症は年に
1〜2名
入院を必要とする細気管支炎は年に5〜10名
|